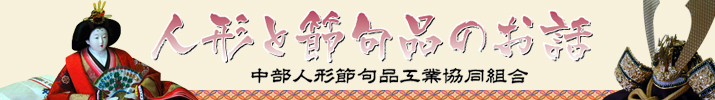尾山人形
愛知県、岐阜県は主要な産地となっています。いわゆる芸者姿のお人形で、歌舞伎の女形(おやま)からきた呼び名といわれています。版画や羽子板などにもよく見られるように、歌舞伎役者は時代のアイドルでいろいろなものに写されてきました。
江戸時代後期には生き人形という、胡粉を用いた仕上げで生きているような表情の人形が作られ歌舞伎の題材にもなっていますが、この頃にこの胡粉を使った人形頭の技術が確立しています。一般にも多くの作品が作られるようになり、昭和40年代ころには結婚や新築などあらゆるお祝いの贈答によく用いられました。その後樹脂の頭が考案され、廉価な作品が作られると爆発的に売られるようになりましたが、やがて、良品が減ってくるに従い衰退の傾向をたどるようになりました。舞踊人形も尾山人形と同種のもので、藤娘や道成寺といった日本舞踊を題材にとった人形です。
結婚や新築のお祝いにこの尾山人形は用いられますが、なにか新しくことを始めるにあたっては、その土地、その場の神々の障りを受けないよう、人形に肩代わりをしてもらうために飾ったものです。
美しい尾山人形や舞踊人形は「厄除け」という意味にとどまらず、お部屋の雰囲気をなごませ華やいだ気分にさせる力を持っています。
|
|
市松人形
単に「市松」とか「いちま」と呼ばれる人形で愛知県は主要な産地です。一般におかっぱ髪の振袖を着た人形ですが、明治大正のころは男の子の姿もたくさん作られました。市松人形というとそれらを含めて小さな子や少女の姿ですが、江戸時代や明治時代には、三つ折れ人形という手足が動き、正座もできるような人形も作られていました。
市松人形の名前の由来は江戸時代の歌舞伎役者・佐野川市松からきたもので、当時人気の市松丞の似姿人形が大当たりしたものなのです。格子柄の「市松模様」も、この市松丞が着用して人気を博し、名付けられた柄です。
このように、「市松」は市松丞にちなんでつけられた名前、一方、「三つ折れ人形」は手足が自由に動くように考えられた構造上からつけられた名前なので、「三つ折れの市松人形」も、「折れない市松人形」もあります。首とヒジ、ヒザだけが動くものが多かったのですが、現在はほとんどが台に固定され動かない市松人形になっています。これは、昭和20年代ころまでは和裁のできる方が多く、裸の市松人形を求めてご自分で着物を作られることもあったからですが、今ではご自分で着せる方はほとんどなく、着せ替えができるようにヒジ、ヒザが動く必要がなくなったからです。昔は、親が仕立てた着物を脱がせたり着せたり、抱っこしたりして遊んだものでしたが、時代が変わって現在では見るだけのことが多くなってきました。これは、衣裳や頭などかなり良いものになってきたことにも原因があるようです。
古い市松の中には、お顔の胡粉が何十年もの歳を経て硬化し、白磁のようなツヤを帯びて、まるで生きているかのような生き生きとした表情のものがあります。高い技術を持った人形師の誇りを、私たちはそこに見出します。 |